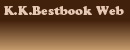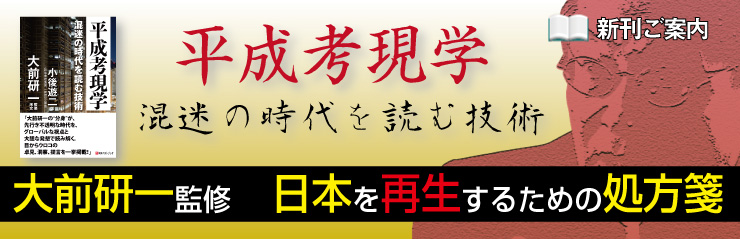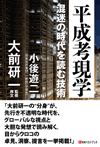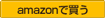◆ 津波プレイン(2011年5月号)
「津波プレイン」という考え方が東北復興で確立されれば、新たな国づくりのモデルができる。 そうすることで、災害の度に繰り返される巨大な公的資金の流出、 国債の発行や納税者の負担、あるいは被害者の泣き寝入りを防ぐことができる。
東日本大震災は未曾有の天災ではあったが、こうした大災害は今回が〝初めての経験〞ではない。政府は「1000年に1度の地震と津波」とすぐに言い訳を並べるが、歴史的に見れば19世紀まで日本は巨大津波に何回か襲われているし、1924年の関東大震災では14万人が火災で命を落としている。1960年に発生したチリ地震では、環太平洋全域を津波が襲い、日本でも三陸沿岸を中心に被害が出て142人が死亡した。このときの教訓を、今回の東日本大震災で生かせなかったことを考えると、やはり「発想」の大転換が必要だ。オーストラリアでは、たとえ1000年に1度であっても洪水被害を受ける可能性のある土地は「FLOOD PLAIN(フラッド・プレイン、水没地区)」と明示しなくては売買できない。そういう場所をあえて買う人は、土地が水没しても文句は言えず、政府に「保証しろ」と迫ることもない。それでも近隣の相場価格の半値以下となれば、買う人はいる。要は、土地所有には一定のリスクがあり、所有者が相応のリスクを負担するということだ。そうでなければ政府は災害復興などで無限のリスクを背負い込むことになり、結果として、国民負担に歯止めがかからなくなる最悪の状況が生じかねない。
東日本大震災は地震よりも津波の被害の方がはるかに甚大だった。被災地では、昔からの経験をもとに津波の「限界標識」を建てられていたが、今回の津波でその限界標識は引き上げられた。つまり、破壊された地域はすべて津波プレイン内ということである。津波プレイン内にある土地の価値は、当然のことながら大幅に下がる。今後は、リスクを承知のうえでそこに家を建てれば、万一災難にあった場合に公的支援は受けられない。しかし、東北復興のためには、被災した土地を放棄し、それを公的な用途に使えるような形で提供すれば政府が代替地と一定の住居を高台に造るといった、「災害構想プラン」が欠かせない。このプランを実行に移すための大前提は、「津波プレイン」の境界線を確定し、また代替住宅街の見取り図を示すことである。菅直人首相はこのような作業を自らやるべきで、復興会議のような烏合の衆に委ねるべきではない。首相に指導力があれば、その程度の作業は数人いればできるはずである。
日本は世界でも屈指の天災列島である。「津波プレイン」という考え方が東北復興で確立されれば、それを全国に拡げて吟味・検証ができる。そうすれば新たな国づくりのモデルができる。そうすることで、災害の度に繰り返される巨大な公的資金の流出、国債の発行や納税者の負担、あるいは被害者の泣き寝入りを防ぐことができる。
例えば「火山」。少なくとも休火山の場合には過去の噴火履歴が数世紀にわたり残っているはずなので、危険地帯を指定することは可能である。「河川」についても同様で、フラッド・プレインがはっきりしている。地震の際に液状化しやすい土地も、わかっているものは開示を義務づける。今度の大地震で、千葉県浦安市などの不動産価格は大幅に下落し、臨海部のマンションの価格も大きく下がっている。東京都の場合、臨海部には埋め立てによって造成されたゼロメートル地帯が広がっている。軟弱プレインに指定され地価が大幅に下がると同時に、地盤改良を求める住民の圧力が増すと想像がつく。
12年間も知事を続けながらオリンピック誘致くらいしかやってこなかった怠け者知事も、これで主任務が明確になるだろう。土地を売買する際には、その土地や地域、環境について分かっていることを明示させる。そのための法律を通すのが急務である。そのうえで、そうした土地のリスクを承知して売買契約を結ぶことを義務づける。そうすれば、災害被害者を少なくすると同時に、予期せぬ公的負担を軽減することができる。東日本大震災は、日本人に多くの意識革命をもたらした。新しい国づくりに活かすための教訓の1つが、津波プレインと、その延長線上にある「災害メモリ付き不動産鑑定法」である。