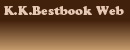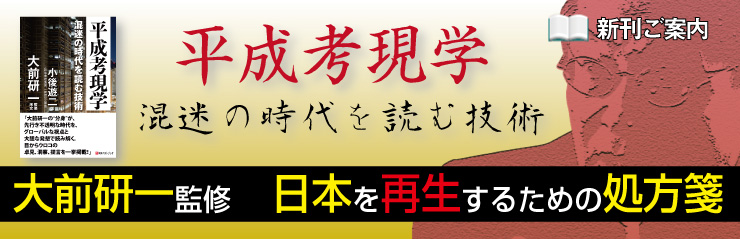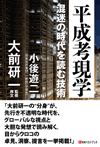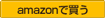◆ 国産信仰と農産物表示(2006年12月号)
日本という国は感情の支配する国である。BSEで大騒ぎしたおかげで牛肉の値段が上がったが、値段が上がれば誰が儲かるのか? とは考えない。 種牛、穀物、飼料のほとんどを海外(それもアメリカ)に依存していて、どうして国産の方が安全だと言えるのだろうか?
北朝鮮からの輸入が制限されたことでアサリやハマグリの値段が高くなった。 このままいけば来年の潮干狩りは期待薄である。 北朝鮮産の小さなアサリを砂の中にまいて、それを拾わせる潮干狩りが木更津や金沢八景などで何年にもわたって行われてきた。 一般消費者がスーパーで買うアサリも、国産表示がしてあっても輸入物が大半である。 日本のどこかの干潟に数週間、埋まっていれば「国産」と名乗ることができるからだ。 このように、日本では農水産物の原産地証明がないがしろにされてきた。理由は2つある。 1つは消費者がいわれもない国産信仰を持っているから。 2つ目はコストが国産では途方もなく高くなってしまうからである。国産信仰の最たるものは牛肉であろう。 日本の100倍以上の飼育数を誇るアメリカで3頭のBSE牛が発見された。 日本では18頭も発生しているというのに、日本人はなぜかアメリカの方が危険だと騒ぎ立てる。 全頭検査をしていないからだ、という学術的になんの根拠もない議論を持ち出してアメリカ産の牛肉を閉め出してしまった。
日本という国は感情の支配する国である 。BSEで大騒ぎしたおかげで牛肉の値段が上がったが、値段が上がれば誰が儲かるのか? とは考えない。 種牛、穀物、他飼料をほとんど海外(それもアメリカ)に依存していて、どうして国産の方が安全だと考えるのだろうか? わたしには理由が分からない。世界で一番牛肉がうまいのはアルゼンチンである。 牧草で育った赤身の肉は日本人の好きな霜降り肉とは違うが、健康食品としてももてはやされている。 岩塩をふりかけたジューシーなステーキは世界的に大人気である。しかし、この肉も日本では輸入が禁止されている。 かなり昔にアルゼンチンで口蹄疫が発生したときに輸入禁止になり、そのままになっているからだ。 その後2005年1月にワクチン接種を条件に、アルゼンチンの南緯42度以北の地域が口蹄疫清浄地域の地位を取り戻し、 アメリカ、カナダ、中国向けの、生鮮・チルド・冷凍牛肉の輸出が解禁された。 しかし日本政府の反応は鈍い。 要するに、原産地国を開示したうえで消費者に選択を任せる、という大人の対応ができないのだ。 すべて「国が責任を持って」対応してしまうのである。
農水産物は、安全性が最も大切なのはいうまでもない。 しかし肝心なのは価格と安全のバランスだ。 外国産がいとも簡単に国産となってしまうカラクリの中で、 農水省が本当に国民の安全を基準として判断しているのか、それには大きな疑問が残る。 食糧の半分以上を輸入に頼る我が国で、もし国が安全性に最終的な責任を持つというなら、 飼料や肥料の追跡も必要で、そのための検査官を全世界に駐在させなくてはいけない。 オーストラリアでは、スポーツフィッシングで捕まえたカジキマグロを食料にすることが、 水銀含有量が多すぎるという理由で禁じられている。 また、日本向けの霜降り肉は脂肪過多で健康に害があるということで市販が禁止されている。 日本では〝無農薬〞といいながら、 実際には、農薬として認められていない薬品が使われていてむしろ危険性が高い、というケースがある。 この問題をどうするのか? 「国産ワイン」というのは発酵を国内で行った場合の呼称であって、 原材料のブドウあるいは濃縮果実ジュースは国産でない場合が多い。 もし原材料のブドウに何らかの問題があれば、国産であっても安全ではないということになる。 実際、バルクワインを輸入して混合しているのに「国産」とか「ご当地ワイン」として売り出しているケースは少なくない。
私の提案は極めてシンプルである。 電気製品や工業品のように世界に通用する安全基準を設け、先進国全体でこれを共有する。 製法や原材料などを含む原産地の表示方法に関しても国際的なルールをつくる。 そして、それに適合しているものについては世界的なスケールで流通性を保証する。 こうすることで消費者が世界で最も良くて安いものを安心して選択・購入できるようにする。 それが「国の役割」ということになる。 特許でさえも今では先進国で共通の申請・承認プロセスを採用しようという時代になっている。 欺瞞表示がまかり通っている農水産物にも、同じようなプロセスが適用されることを望みたい。